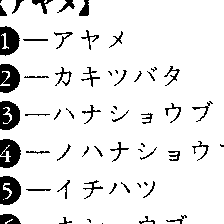改訂新版 世界大百科事典 「アヤメ」の意味・わかりやすい解説
アヤメ
flag
Iris sanguinea Donn.
シベリア,中国東北部,朝鮮,日本に産し,日本では各地の山間の草地に生えるアヤメ科の多年草。紫色の風情のある花のため,庭植えもされる。茎は高さ30~60cm。葉は先が垂れるために短く見えるが,茎とほぼ同長であり,また二つにおりたたまれて表面がくっつきあったため,両面とももともとは裏だった面からなる単面葉で,幅約1cmの線形剣状である。和名は葉が2列に並んだ様子の文目(あやめ)の意味から,あるいは花の外花被の基部に綾になった目をもつことから名付けられたという。昔アヤメと呼んだのはサトイモ科のショウブのことであった。花は直径約8cm。赤みを帯びた鞘(さや)状の苞葉の間に普通2花を有し,花期は5月。幅の広い外側の3枚は外花被片で,基部は黄色に紫条,中央にかけては白地に紫条のマークがある。花冠中央に直立した3枚の弁が内花被片で,その間から花弁様に3方に平開しているのは花柱枝で,先端部にめしべがある。おしべは花柱枝の内側にあり,その奥には蜜腺があって,虫が花柱の下へもぐりこむ際に花粉がこすりつけられるのが,アヤメをはじめアヤメ属の花のしくみである。アヤメは白花や通称三寸アヤメと呼ばれる矮性の白花,紫花が見られ,まれに筋入り,斑咲き,藤桃色や分枝するもの,内花被片が外花被片様になった6弁咲きもある。
アヤメ属Irisは北半球温帯に約200種が広く分布し,多くが観賞用に栽培される。
カキツバタI.laevigata Fischerはシベリア,中国東北部,朝鮮,日本の水辺に野生し,アヤメ属中最も水を好む。5月に青紫まれに白色の花を1茎に通常3花つける。日本ではアヤメ属中最も古くから親しまれ,《万葉集》にも詠まれた。花で衣を染めたため,カキツケバナが語源という。バイカル湖近辺で発見されたものに,1837年に学名がつけられた。イギリスでは1920年ごろハナショウブと混同されていた。カキツバタは外花被片の中央に1本の白線が目だち,アヤメは網目模様があり,ノハナショウブは黄色の線が見られるので区別できる。茎は長さ50~70cmで分枝せず,葉は淡緑色で幅広い線形剣状で長さ40~80cm,幅2~3cmで中肋は隆起しない。花は径12cmくらいで,外花被片は楕円形で中央部に1本の白線が見られ,内花被片は倒披針形で直立する。園芸品種は約20あり,そのうち矢車,鷲の尾,御所紅(べに)や光格天皇の遺愛の折鶴が有名で,斑入葉や四季咲きもある。イギリスでは約4種ほどが育成された。日のよく当たる水湿地を好み,池畔に適する。アメリカ原産の近縁のイリス・ウェルシコロルI.versicolor L.との交雑種が1968年に作られた。
イチハツI.tectorum Maxim.(英名roof iris)は中国の中央部から西部とミャンマー北部に産し,古く日本に渡来した。1563年(永禄6)の古文書に初めて書かれており,その後《花壇綱目》(1681)などいくつかの古い園芸書に〈一八〉や〈一初〉の名で見られる。漢名は鳶尾(えんび)という。葉は長さ40cm前後,幅3~4cmの剣状であるが,半ばより垂れる。茎は1,2分枝し,3~5花をつけ,藤紫色の花は径10cmくらいで楕円形の内花被片が開き6弁様になる。外花被片は円形で,縁がやや縮れ,濃紫色の脈と斑点があり,基部から中央にかけて白色のとさか状突起があるのが特徴である。4月下旬から開花し,早く咲くのでイチハツの名がつけられたといわれる。白花や斑入葉も見られ,7花も咲くものやイリス・パリダI.pallida Lam.との雑種も作られている。古く,わら屋根にも植えられ,大風を防ぐとされていた。中国では根茎を薬用にし,絵画にも描かれる。
シャガI.japonica Thunb.は中国,日本に産する。古く中国から渡来したと推定され,低山地に群生している。葉は常緑で表面に光沢があり,茎は七つ前後に分枝して,枝ごとに次々と25輪くらいの1日花をつける。走出枝で増えるのが特徴である。葉は長さ45cmくらい。幅2~3.5cmの剣形で扇状になり,一方に傾く。花は直径約5cmで白く,外花被片は倒卵形で縁に細かい切れ込みがあり,中央に橙色のとさか状突起と橙色と紫色の斑をもつ。内花被片はやや小さく平開し,6弁様になる。花期は日本に野生するアヤメ属中最も早い4月。日本のものは三倍体で種子は実らないが,中国のものは実るといわれている。まれに斑入葉がある。また海外では産地の違うシャガどうしの美しい交配種,近縁のイリス・コンフサI.confusa Sealyとの雑種も作られている。シャガのように外花被片にとさか状突起をもつイリスは世界に11種がある。
エヒメアヤメI.rossii Bakerは朝鮮,中国東北部や日本の北九州,四国,山陽地方に自生し,まれに見られる小型の植物で,低山地の草原に生える。茎,葉とも高さ30cm内外,花も小輪でかれんで,古くからタレユエソウの名がある。ヒメシャガI.gracilipes A.Grayは同様に小型の植物で,本州,四国,九州の低山地に自生し,花は淡紫色で白花もあり,山草愛好家に好まれる。外花被片にとさか状の突起がある点でシャガと仲間である。ヒオウギアヤメI.setosa Pall.は本州中部以北,北海道,アジア北東部,アラスカ,カナダにかけて分布し,内花被片が針状で小さく目だたない。ノハナショウブは葉の中脈が明りょうで,花はカキツバタに似るが,外花被の基部の線が黄色である。栽培されるハナショウブは本種を日本で改良したもので,花が大きく多数の品種がある。キショウブI.pseudacorus L.(英名water flag/yellow flag)はヨーロッパ原産で繁殖力が強く,日本の湿地や池辺にも野生化している。葉はハナショウブに似るが,濃緑で中肋がより隆起する。分枝し多花性で,花は黄色の1日花である。品種には淡黄のバストールディーBastardiや,白花,八重咲き,斑入葉などがある。アヤメ近似の朝鮮産のカマヤマショウブI.thunbergii Lundst.は花色が濃紫色で切花に使う。近縁のヨーロッパ産のコアヤメI.sibirica L.は小輪で花茎が葉よりも高く,分枝し3~5花をつける。中国の雲南省近辺産のイリス・クリソグラフェスI.chrysographes Dykesはアヤメに似て,仲間には約5種がある。チャショウブI.fulva Ker-Gawl.(英名copper iris)はアメリカのミシシッピ河畔に産し,花は茶褐色。ネジアヤメI.biglumis Vahlは葉がねじれる特徴があり,カンザキアヤメI.unguicularis Poir.は花期が11~3月である。ヨーロッパ産には,ドイツアヤメI.germanica L.など外花被片にひげ状突起をもつ多くの野生種や,スパニッシュ・アイリスI.xiphium L.のような球根アイリスがある。アヤメは水辺でなく,普通の畑地に育つ。カキツバタは最も好水性で水際に適し,シャガ,イチハツはやや日陰の乾燥地を好む。繁殖は株分けまたは実生による。
ネジアヤメの葉はチベットでヤクの飼料や野菜を束ねる縄に用いた。アメリカのオレゴン州に野生するテナックスI.tenax Dougl.の葉で,インディアンは魚をとる網や動物をとるわなを作った。五大湖近辺産のイリス・ウェルシコロルの根茎は薬用にされ,葉は敷物やサンダルに使ったとされる。キショウブは古くフルール・ド・リスfleur-de-lisと呼ばれ,フランク王クロービス1世が紋章にした。ニオイイリスI.florentina L.(英名orris)は根茎を香料や薬用に用いたが,現在ではイリス・パリダを香料用にイタリアで主要な産業作物として栽培している。芳香の主成分はイロンirone。イリス・アルビカンスI.albicans Langeは,イスラム教徒が墓地を飾るためアラビアからヨーロッパに植えられた。
執筆者:堀中 明+矢原 徹一
アヤメ科Iridaceae
単子葉植物でユリ科に近縁。多年草で,地下には根茎または塊茎・球茎をもつ。葉は細長く,二つ折りにたたまれていることが多い。花は内花被片と外花被片を3枚ずつもち,子房は3室。これらの点はユリ科と共通だが,子房下位でおしべが3本に退化している点で異なる。6枚の花被片は花弁と萼片の区別がなく着色しており,虫媒受粉に適応して色彩や模様が進化している。アヤメ属では花柱が花弁状に変形している。果実は蒴果(さくか)。美しい花をつける植物が多く,観賞用に栽培されるものが多い。一般的に陽地性の植物であり,栽培植物としては利用しやすい特性を備えている。アヤメ属(アイリス,ハナショウブなど),サフラン属(クロッカス),フリージア属,グラジオラス属などが日本では普及している。サフランの花柱(サフロン)やニオイイリスの根茎は芳香成分を含み,香料として用いられ,かつては鎮静剤として薬用にした。
執筆者:矢原 徹一
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報