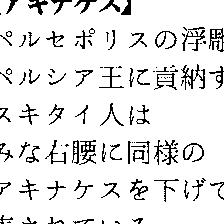改訂新版 世界大百科事典 「アキナケス」の意味・わかりやすい解説
アキナケス
akinakēs[ギリシア]
前7世紀末から前4世紀前半にかけて,メディア人,スキタイ人が愛用した鉄剣。全長60~80cm。心葉形の鞘口の一側に孔をあけた耳状の突起があり,これによって腰帯に懸垂し,鞘尻に鐺(こじり)を設けてここに革紐をつけて大腿部に結びつける。柄や鞘にはアニマル・スタイルの打出し文をもった黄金の飾板をかぶせる。同じ頃のペルシア人の剣は,ペルセポリスの浮彫によると,剣身が幅広で短く,腰帯に斜めに挿し込んで佩用した。ヘロドトスは《歴史》において〈ペルシア語でアキナケスというペルシア風の短剣〉と呼び,またスキタイ人も同様な剣を佩用していると述べているが,これは同じアケメネス朝を構成するメディア人とペルシア人とを混同したものであろう。アキナケスは前6世紀後半に西はドナウ川流域,東は南シベリア,モンゴリアから中国北辺に波及した。後者は鋳造の青銅製で剣身が短いので,アキナケス式短剣と呼んで本来のものと区別すべきである。中国の史書にみえる〈径路刀〉をアキナケス式短剣とする考えがある。
執筆者:山本 忠尚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報